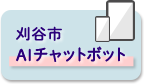学芸員のひとりごと 令和4年10月~令和5年3月
郷土資料館にトヨモーターがやってきました (2月28日)

1台のオートバイが愛知県農業総合試験場(長久手市)から刈谷市に譲渡されました。昭和24年(1949)に刈谷町(当時)で設立されたトヨモータースが製造したオートバイ・「トヨモーター」です。
トヨモーターの「トヨ」はトヨタに由来しますが、トヨタグループの企業ではありません。しかし、トヨタグループのひとつ・刈谷工機(現・ジェイテクト)の工場を借り受け、日新通商(現・豊田通商)が資金面で支援していました。さらに、販売面でも日新通商が総代理店となり、愛知トヨタ自動車をはじめとするトヨタ自動車を販売する地方ディーラーと代理店契約を結んでいるといったように、トヨモータースはトヨタグループと深いつながりのある企業でした。

農業総合試験場に残されていたこのトヨモーターは、愛知県の農業改良普及員が移動するために使っていたものです。
農業改良普及員とは、昭和23年に施行された農業改良助長法によって定められ、国と県の共同事業として実施された制度・協同農業普及事業にあたった専門職員です。普及員は、担当区域の農家を訪問して助言などを行っていたため、交通手段としてオートバイが使用されていたのです。昭和38年には、普及員のほぼ全員分にあたる263台ものオートバイが配車されていました。昭和40年代以降は、オートバイにかわって四輪自動車が配置されるようになりました。

さて、このトヨモーターをよく見ていくと、車体のフレームに「TB-891」、エンジンには「T8-11040」とあります。
昭和30年に発売されたトヨモーターのTB型のフレーム、T8型のエンジンであることを示しています。つまり、TB型の車体にT8型のエンジンを搭載しているのです。
TB型の方がより堅牢なフレーム、前後サスペンションの高性能化がみられ、豪華な仕様となっていたので、合理的な組み合わせといえます。

ところで、農業改良助長法によって、農業改良普及員と同様に生活改善普及員が配置され、各地で生活改善を進めました。生活改善の大きなミッションの一つは台所、すなわちかまどの改良でした。
郷土資料館では、トヨモーターのとなりに生活改善の中から生み出された「改良かまど」が展示されています。昭和30年代の復元家庭とともに、農業改良や生活改善の様相をご覧いただけるようになっていますので、ぜひご覧ください。
―参考文献―
神谷剛生編『トヨモーター展-メイド・イン・刈谷のオートバイ物語-』(刈谷市美術館、平成30(2018)年)
愛知県農業水産部農業技術課編『愛知の普及事業のあゆみ 農業改良普及事業50周年記念誌』(愛知県、平成10(1998)年)
図書コーナーに新しい本が追加されました!(12月25日)
刈谷市歴史博物館では定期的にエントランスの図書コーナーに新しい書籍を追加しています。
書籍は、歴史に関係するものを中心に、一般書、漫画、絵本などを揃え、子供から大人まで楽しんで読書をしていただけるように選んでいます。
今回は約30冊の新しい書籍を追加しました!
その中から私のおすすめを3冊紹介します!!
絵本『たかこ』
ある日、「たかこ」という女の子が転校生として学校にやってくるお話です。たかこは着物を着て、扇を持ち、周りとは少し変わった言葉遣いで話す子です。そんなたかこが、クラスで起こる様々な出来事を通してみんなと認め合う様子や、たかこの自分に正直な性格は現代社会においても学ぶものがあると思います。
漫画『ねこねこ日本史11』
「ねこねこ日本史」は歴史上の人物を「ねこ」で表現した、みんなに大人気のシリーズです!
『ねこねこ日本史11』は、古代から近世の偉人12人に焦点を当てたものとなっています。私自身、文字ばかりの難しい本は得意ではないので、かわいらしい猫のキャラクターと読みやすい4コマ漫画で楽しく歴史を学ぶことができました。大河ドラマで注目された北条義時も登場しています。
一般書『縄文人も恋をする!?』
多くの著書で縄文時代の魅力を伝えている研究者・山田康弘さんが、縄文人の恋愛事情など、皆さんが気になる縄文時代の素朴な疑問に答えます。専門ではない方に向けて書かれているので、「縄文時代、気になるけど、難しそう・・・」と思っている方にもおすすめです。もちろん縄文時代が大好きな人も楽しむことができると思います。また、この本はQ&A方式になっているため、自分の気になる疑問から読み進めることができるのも個人的にポイントが高い部分です。
今回は3冊のみの紹介となりましたが、この他にも魅力的な本がたくさん追加されています。展示をご覧になった後にこちらの本でより深く勉強するのもおすすめです。
図書コーナーには今後も新しい本を追加していく予定ですので、皆さんもおすすめの本がありましたらぜひ教えてください!
(学芸員:野村)

縄文時代のものづくり ―石鏃を作ってみよう- (10月28日)
皆さんは石鏃(せきぞく)という石器を知っていますか?
石鏃とは1万年以上続く縄文時代を通して使われた代表的な道具の一つで、俗称では「矢じり」とも呼ばれています。先端が鋭く尖り、三角形をしているものが一般的で、縄文時代の人々がシカやイノシシなどの動物を狩猟するときに使った矢の先端に装着されました。写真の丸の部分が石鏃です。

刈谷市では縄文時代の遺跡がたくさん発見されており、一か所の遺跡から300点以上もの石鏃が出土することもあります。このことから縄文人は日々たくさんの石鏃を作っていたのかもしれません。
では、縄文人たちは石鏃をどのように作っていたのでしょう。
今回は石器の材料としてよく使われた石、黒曜石を使って石鏃の作り方の一例を紹介していきます。
まず、石鏃を作るための道具を準備します。今回は黒曜石を粗割りする時にハンマーとして使う河原石や鹿角、後で紹介する押圧剥離(おうあつはくり)に使う鹿角の先端を使っていきます。石鏃に使われる石は黒曜石のようなガラス質の石が多く、破片が飛び散ることもあるので、目を保護するためのゴーグル、手を保護するための手袋や動物の革などを準備して行うのがおすすめです。

では、実際に石鏃を作っていきましょう。石鏃の素材に向いているのは剥片と呼ばれる石のかけらで、薄く、湾曲の少ないもので、完成した石鏃の形を想像することができるものが適しています。そのため、まずは黒曜石に河原石のハンマーや鹿角ハンマーで直接打撃を加えて粗割りし、石鏃作りに適した剥片を剥離していきます。石を割る時は力任せに割るのではなく、ハンマーの重みを利用して割ると良い剥片を剥離しやすいと思います。


次に、剥離した薄い剥片を河原石のハンマーで割っていき、石鏃の大まかな形を作っていきます。この作業で余分な厚みをできるだけ取り除いておくと完成品も薄くきれいなものに仕上がりやすくなります。この時も力任せに割ると折れたりしてしまうので、軽くコツコツと割っていくと割りやすいです。


なんとなく石鏃の形ができてきたら、鹿角の先端を使って押圧剥離で細かい加工を繰り返しながら、仕上げていきます。押圧剥離とは、これまでの工程のハンマーで黒曜石に直接打撃を加えて割る方法とは異なり、鹿角の先端部を縁辺に押し当てて圧力で押し剥がす技術になります。石の縁辺を削るのではなく、縁辺から内側に向かって力を加え、薄く石をめくるイメージで行うのがコツです。

最後の細かい加工が終わり、自分の納得できる形に仕上がったら完成です。
石器作りは見栄えのする石器を作ることも楽しみの一つですが、大切なことは製作する中で石器を観察する眼を養うことだと思います。そうすることで、様々な種類のハンマーによる剥離痕の違いや、石器に見える割れ面の構成から、どのようにその石器が製作されたかなど、石器自体を眺めているだけでは気付きにくかったことを教えてくれることがあります。また、日々、石器作りを行うことによって、当時の人の身振りや製作時の意識などが見えてくる可能性もあるかもしれません。
今回は黒曜石を使って石鏃を作ってみましたが、ガラス瓶の底や海岸で拾うことができるシーグラスなどでも作ることができます。ガラスの色によっては青や緑などきれいな色の石鏃も作ることができるので、皆さんもぜひ挑戦してみてください。

このページに関するお問い合わせ
歴史博物館
〒448-0838
刈谷市逢妻町4丁目25番地1
電話:0566-63-6100 ファクス:0566-63-6108
歴史博物館へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。